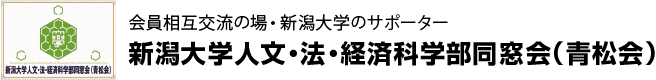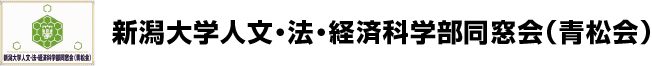令和7年度に向けて
人文・法・経済科学部同窓会
会長 高木 裕(S48年・人文卒)
※高木会長は、去る令和7年8月2日に逝去されました。在りし日を忍び心よりご冥福を
お祈りいたします。
会則に基づき当面の間、石川恵三副会長が会長職を代行いたします。

ロシアによるウクライナ侵略、パレスチナ自治区ガザの紛争と人道問題など、世界情勢は目まぐるしく動き、大国も覇権を競い合う昨今。そんな中、日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことは暗い世相に一筋の光明をもたらしてくれました。
さて、コロナが猛威を振るった時期を乗り越え、ようやく本同窓会の各支部でも交流活動が再開されています。交流を旨とする同窓会ですから、リアル開催で仲間の顔を見て、語り合うことがいかに貴重かということがよくわかりました。昨年、私も久しぶりに首都圏支部の総会に参加して参りました。
講演会では石井正一氏(S48年・経卒)が関わっておられる国家的プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期」の取り組みについて詳しいご説明がありました。石井氏が、理系の知識と発想が全体を占めるプロジェクトにPDとして参画され、活躍している姿はとても同期の人文学部卒とは思えない活動であり、大いに刺激を受けました。やはりスクリーンの向こうではなく、対面で交流することの意義を再確認しました。本同窓会は全国に11の支部組織がありますが、今年度の活発な交流活動に期待したいと思います。
卒業生のみなさんへ
2025年春、卒業生を送り出す時が来ました。人文学部、法学部、経済科学部をご卒業するみなさん、このたびはご卒業おめでとうございます。人文・法・経済科学部同窓会を代表して、心からお慶び申し上げます。ご入学直後は、コロナ感染が拡大を続けている日々で、ZOOMなどを活用した授業で、なかなか対面授業を享受するわけにはいかず、もどかしい思いをされたことでしょう。このような苦労をされたことをバネに、大学で修養したことを糧として、堂々と社会に臨んでください。三学部同窓会は新潟本部の他に、首都圏など各地に11支部があり、活発に交流を行っています。ぜひ、本部、支部の同窓会活動にご参加ください。
入学生のみなさんへ
この春、ご入学のみなさん、ご入学おめでとうございます。同窓会へのご入会ありがとうございます。 本同窓会は、令和5年に創立70周年を迎えました。文学科、法学科、経済学科を備えた人文学部として出発しましたが、いまでは学生定員も人文学部(210名)、法学部(180名)、経済科学部(350名)を抱える三学部となりました。その母体の人文学部が本同窓会の原点にあります。
本同窓会は、在学する皆さんのためにさまざまな支援プログラムを用意しています。学部生の論理的思考力と日本語表現力の向上を目的とした「青松賞懸賞論文」制度、また、同窓会独自の基準による「奨学金」制度も設けています。これからの4年間、充実した学生生活を送られることを心から願うとともに、みなさんの活動を応援してゆきます。